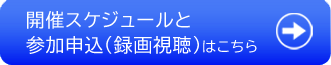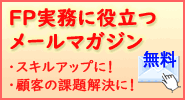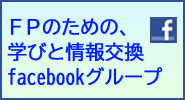遺族の必要保障額
必要保障額の確認方法
※世帯主死亡時の配偶者の必要保障額について説明していますが、配偶者死亡時の必要保障額も、考え方は同じです。必要に応じて、適宜読み替えてください。
画面で確認する手順
1.メインメニュー画面
メインメニューに戻ってください。メインメニュー画面下部の「シミュレーション結果を表示する」ボタンを押します。
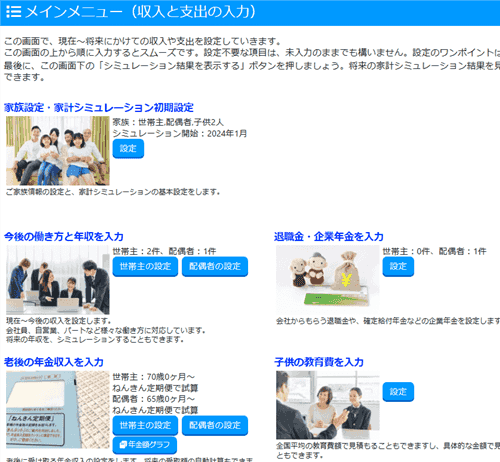
・
・
・
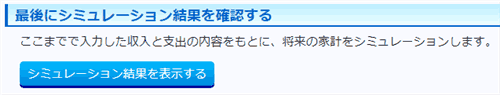
2.シミュレーション結果画面
シミュレーション結果画面下部に、「家族が万が一の場合のシミュレーションも行う」にチェックが入っていることを確認します。
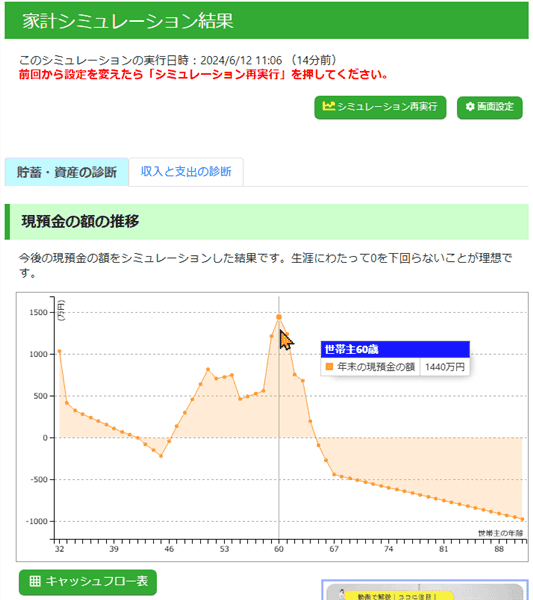
・
・
・
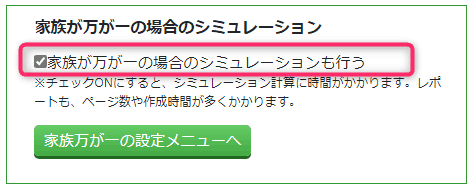
もしチェックが入っていなければ、チェックを入れて「家族万が一の設定メニューへ」のボタンを押してください。
このボタンを押した後のメニュー画面を開き、「遺族生活設定を入力」画面で必要事項を入力して下さい。その後、再びシミュレーション結果画面に戻ってきます。
3.世帯主万が一の場合の分析結果
上記2の操作を行うと、家計シミュレーション結果画面に「表示切替」というドロップダウンが表示されます。その中から「世帯主万が一の場合の分析結果」を選択します。
その次に、「生命保険の診断」というタブを押してください。
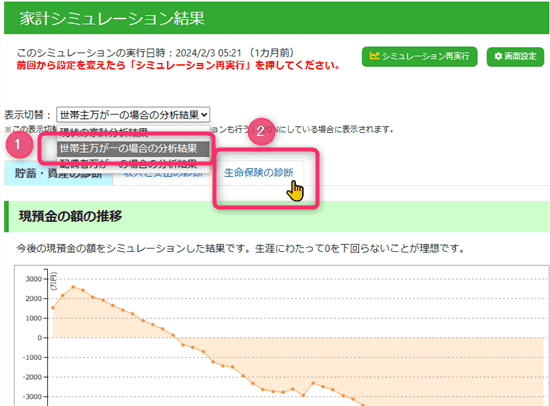
4.必要保障額の表示
「生命保険の診断」タブに、必要保障額のグラフが表示されています。
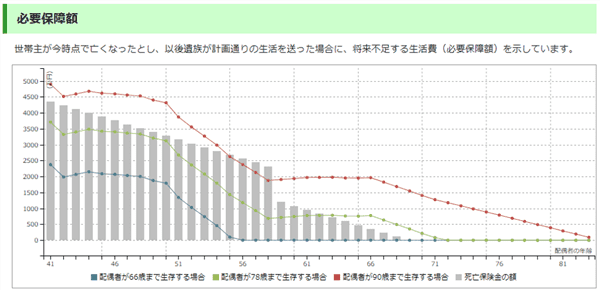
レポートでの確認方法
「遺族の必要保障額」のページをご覧ください。
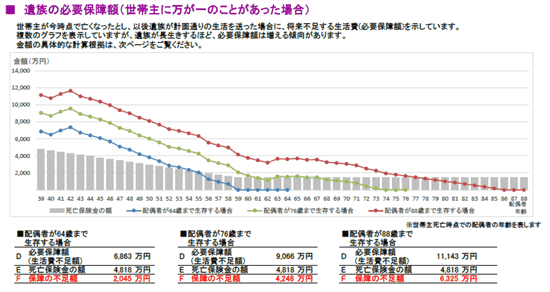
必要保障額グラフの見方
※世帯主死亡時の配偶者の必要保障額について説明していますが、配偶者死亡時の必要保障額も、考え方は同じです。必要に応じて、適宜読み替えてください。
折れ線グラフが必要保障額
今時点で世帯主が死亡した場合に、今後遺族の生活費がどれくらい不足するか(=必要保障額)を計算し、折れ線グラフで表示しています。
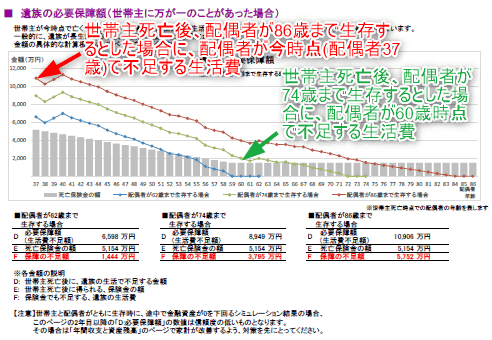
世帯主の死亡後、配偶者が特定の年齢まで生存する場合(3パターンの年齢を用意しています)の金額が表示されています。
一般的には、遺族が長生きするほど、必要となる生活費は増える傾向にあります。
(収入、支出の状況によっては、その限りでないこともあります)
グラフの横軸は、世帯主死亡後における配偶者の年齢です。
(世帯主の死亡時点の年齢を表しているのではありません)
棒グラフは死亡保険金の額
保険(死亡保障の入力)の画面で登録した死亡保険金を、棒グラフで表現しています。
折れ線グラフの必要保障額と、棒グラフの死亡保険金の額を比較すると、遺族の貯蓄が底をつかないためには、あといくら保険金を上乗せすればよいのか(追加の資産が必要か)を示しています。
必要保障額の計算根拠
1年ごとに、それ以降遺族が支出する生活費から、「現在の貯蓄+それ以降に発生する遺族の収入」を差し引いた金額を計算し、グラフ化しています。
そのため、
必要保障額のグラフと、遺族の現預金のグラフとは、ほぼ同じ形となります。
レポートの必要保障グラフの次のページに、「遺族の必要保障額」のページがあります。このページで、必要保障額の計算根拠を確認できます。
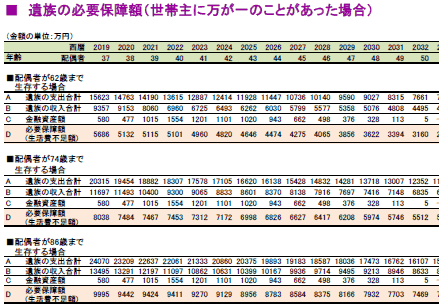
シングルのご家庭の必要保障額について
現在の当ソフトでは、シングルのご家庭(父子家庭、母子家庭)での必要保障額は算出をいたしません。
万一両親とも死亡した場合に、残された子がどのような環境で暮らすことになるのかによって、必要保障額は大きく変化します。
(金融資産が十分な環境で子が育つなら必要保障額は低く、逆にそうでない環境で子が育つなら必要保障額は高くなります)
父母共に死亡した場合の環境を入力する箇所がないことから、現在はこのような場合の必要保障額は算出ができないのです。
シングルのケースの必要保障額を出してほしいという要望は、たびたびFPの方からいただきます。
その場合に当ソフト開発チームより、FPの方に「子が以後、どのような財産環境で育つことを想定していますか?」と質問をさせていただくのですが、ここまで考えていらっしゃるケースはほとんどありません。何か妙案があれば、FPの方と一緒に検討したいと考えています。
簡易的な算出方法としては、遺族キャッシュフロー表の支出額のうち必要な期間を積み上げて加算し、それを必要保障額をする方法があります。
(もちろん、遺族年金や他の収入を考慮して算出してもかまいません。)
※頻繁なバージョンアップにより、本ページの記述・画面イメージの一部が古くなっている場合があります。お気づきの点・ご不明点がございましたら、お問い合わせのページよりお知らせください。
![]() 家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから
家計分析レポートサンプルのダウンロードはこちらから
一般消費者(個人ユーザー)向けに「夢を叶え、未来を創る、ライフプラン講座」を2026年から開催します!
Zoom参加OK・録画配信あり